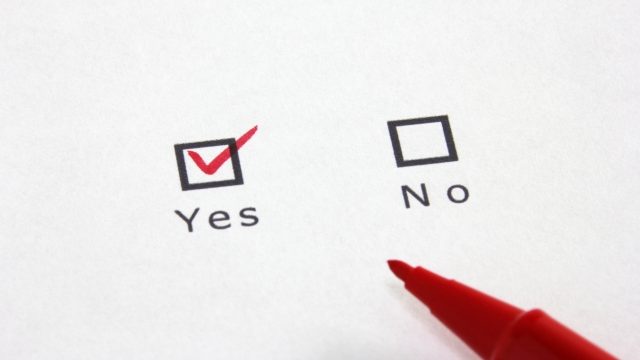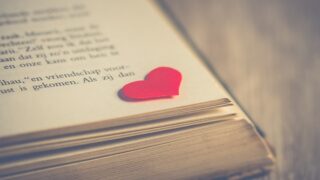※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
あなたは将来の年金に
期待をしていますか?
経営者には、
「年金なんて期待していない」
「どうせ将来はもらえなくなる」
という考えを持っている方が
多いかもしれません。
ですが、意外なことに、
若いスタッフの方には、
「年金は国が運用してくれるから安心」
「将来の安心のために社会保険に入りたい!」
と考えている人も多いようです。
もし、年金の「真実の利回り」を
知ったうえでそういった考えを持って
いるのならそれも良いのですが、、、
多くの人は、
年金の「真実の利回り」に
気付いていないかもしれません。
利回りを出すためには、
・支払った金額
・もらえる金額
の2つの要素が必要になります。
年金で言えば、
・社会保険料の金額
・将来もらえる年金額
ということになるので
かなりシンプルなはずです。
ですが、実は、
この2つの数値を勘違いさせる
“ワナ”が存在しています。
そして、そのワナにハマった
多くの人が、気付かぬうちに
・自分の認識よりも遥かに高い
投資額を自動的に天引きされて、
・自分の認識よりも遥かに低い
利回りの商品に資金をロック
されている
ということが起きています。
正しい認識をしたうえで
その選択をするなら良いですが…
将来になって「そんなの知らなかった!」
となったら笑えないですよね。
ということで。
今回は、2つの”ワナ”の内容と、
そこからわかる年金の「真実の利回り」
について暴露したいと思います。
あなたが経営者なら
ぜひ自分のスタッフの将来を
守るためにも学んでいって
欲しいです。
では、早速。
————–
1つ目のワナ:
社会保険料は折半ではない
————–
「社会保険に加入したい」という
スタッフの方にその理由を聞くと、
「会社が半額を負担してくれるから」
という回答が返ってくることが
多いです。
ですが、これは真実ではありません。
実際は、そのスタッフの方が
全額を負担することになります。
なぜかというと、経営者は、
「社会保険料の会社負担分も含めた
給与額しか支払うことができない」
からです。
たとえば、
人件費の予算が25万円だとして、
そのまま額面給与25万円を支払った
とします。
社会保険料の会社負担分は約15%
ですから、会社は約29万円のコスト
を負担することになります。
もともと25万円しか予算がないのに、
29万円のコストがかかってしまったら、
その会社はいずれやっていけなくなって
しまいます。
だから、単純な計算ができる
経営者であれば、
会社負担の社会保険料も加味した
額面の給与を設定するわけです。
→今回の場合なら額面給与を
21.5万円程度にすることで、
額面給与21.5万円+会社負担の社会保険料3.3万円
=24.8万円として、25万円の範囲内にコストを
おさえるということ
ここからわかるのは、
もし、社会保険料がなければ、
そのスタッフは額面25万円の給与を
もらうことができたのに、
会社負担の社会保険料があるので、
額面給与が21.5万円になったという
ことです。
この差額は会社負担の社会保険料
ですから、スタッフは、
・会社負担の社会保険料をすでに
引かれた給与をもらっていて、
・さらにその給与から個人負担の
社会保険料を引かれている
ということが言えます。
つまり、国は「会社と個人が折半負担」
と言っていますが、実態としては、
「スタッフが全額負担している」
ということになるわけです。
ちなみにその数値は恐ろしいです。
世の中では「税金が高い」という
ことはよく言われますが、
実際、年収600万円程度であれば、
所得税と住民税を足しても8-9%程度
になります。
ちなみに年収1000万円でも15%程度です。
では、社会保険料はどうかというと、、、
「給与の約30%」です。
しかも、社会保険料は年収によって
保険料率が変わったりしません。
要は、
「年収が低かったとしても、
年収1000万円の税率の2倍の
パーセンテージが徴収される」
ということです。
「半分だけ負担している」
と認識していたのに、
実は給与の30%も自動天引き
されていたと思うと、、、
恐ろしい話です。
————–
2つ目のワナ:
「ねんきん定期便」には
本当の納付額の記載がない
————–
あなたは「ねんきん定期便」を
見たことがありますか?
毎年の誕生日に届くものですが、
見ないで捨ててしまう方も多いかも
しれませんね^^;
実は、このねんきん定期便には、
・これまでの保険料納付額
・これまでの実績に応じた年金額
が記載されています。
つまり、投資した保険料に対する
利回りを容易に計算できるという
ことです。
では、これの2つの数値から
平気寿命まで年金がもらえる仮定のもと
計算してみるとどうなるか?
これは当然、人にもよりますが、
「大体2-3%」くらいの利回りがある
ようです。
ですが、、、
これは真実ではありません。
実はこの表記に”カラクリ”があるのです。
どういうことかというと、
ねんきん定期便に記載されている
「保険料納付額」には
「会社負担の保険料」が
一切入っていないのです。
会社は、社会保険料について、
その半額をスタッフから
給与天引きで徴収して、
残りの会社負担の半額と合わせて
国に納付しています。
ですが、それは”そういった流れで
保険料の納付している”というだけの話で、
あくまでも年金額の元となる保険料は、
「社会保険料全額」になるわけです。
スタッフが半分負担した保険料だけを
もとに利回り計算をしたらおかしいことに
なることは誰しも簡単にわかります。
それにもかかわらず、
「ねんきん定期便」の保険料納付額には
個人負担の保険料のみが集計されている
のです。
さらにいえば、すでに「1つ目のワナ」で
お伝えしたように、実際はスタッフが
会社負担の保険料も負担しているわけですから、
なおさら正しい利回り計算をするためには、
会社負担の保険料も含めなければならないと
言えます。
これらを踏まえて、先と同じ仮定のもと
再度利回り計算をしてみると、、、
実際の年金額の利回りは「1.0-1.5%程度」
になってしまうとのことです。
日本のインフレ目標率は年2%だと考えると、
この利回りでは、結果的に「利息ゼロの商品」
と言えるかもしれません。
これが年金の「真実の利回り」
だということです。
社会保険料について、
被保険者負担と会社負担が
半額ずつであること。
ねんきん定期便についての
保険料納付額は被保険者負担分を
表記していること。
このどちらもウソを書いている
わけではあります。
ですが、知識がないと、
「その表記を正しく認識できない」
ということもまた事実です。
もし、あなたが経営者であれば、
スタッフの方が正しい認識をできるように
今回の話を伝えてあげてくださいね。
桐生 将人