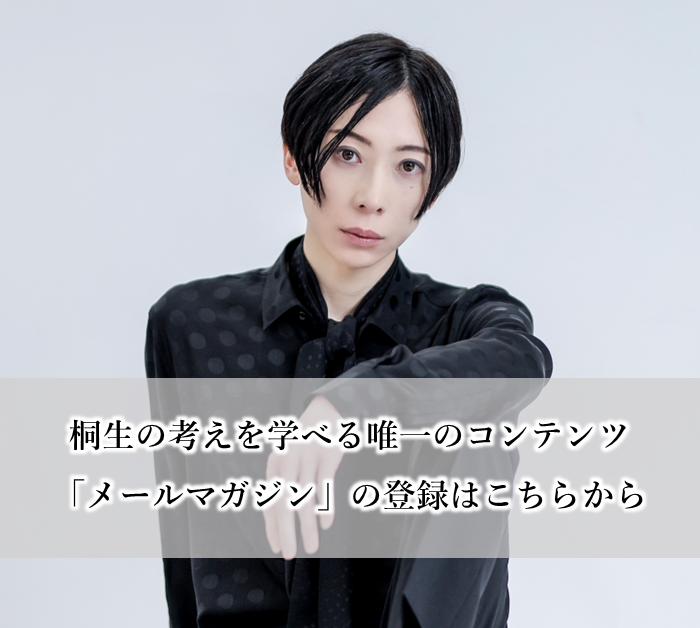※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
今日、おにぎりを作りました。
ある具材をいれて、三角形の
おにぎりをにぎりました。
そこで、、、
せっかくなので、あなたにチャレンジ
して欲しい問題があります。
—————
問題:
桐生のおにぎりの具材はなにかを
当てる方法を考えてください。
制限時間は10秒です。
前提条件:
・具は「鮭、昆布、梅」のどれかです
・写真等はお見せできません
・においをかいだり、食べたりすることは
できません
—————
さて、、、どうでしょう?
わかりましたか?
答えはブログの最後にでも。
なんでこんな質問をしたかというと、
「”どう考えればいいか”を学ぶことで
こういった質問にもサクッと答えられる
ようになる」ということを
お伝えしたかったからです。
先日のメルマガで、
「とりあえず考える」より前に
「どう考えればいいかを学ぶ」ことが
重要だということをお伝えしました。
今回はその続きで、
「より良い考えを生むために、
考えを広げて、深める方法」
について具体的な方法をいくつか
ご紹介します。
では、早速。
—————
考えを広げる:かけあわせ法
—————
考えることにおいて重要なのは、
論理的思考と非論理的思考の両方を
使うことです。
論理的思考は、筋が通りやすい反面、
革新的な発想が生まれにくいという
デメリットがあります。
ですが、「いきなり非論理的思考をしろ」
と言われても難しいですよね。
だから、”考える技術”が必要なわけです。
その1つが「かけあわせ法」です。
たとえば、
・ロボット掃除機ルンバ
・乳酸菌ショコラ
・うんこ漢字ドリル
といったものはかけあわせの典型と
言えます。
どれも、論理的思考では繋がりそうも
ない単語ですよね(特に最後のドリル。笑)。
かけあわせ法のポイントは、
・まず、中心のキーワードを決める
・ひたすら思いつくままに組み合わせて
奇跡の出会いを求め続ける
ということです。
参考までに、参考図書の事例では、
目的:社員の離職を下げる
キーワード:脱離職
組み合わせ例:脱離職ランチ、脱離職休暇、
脱離職表彰、まいにち脱離職、週一脱離職、
脱離職有名人…
といったものが紹介されています。
上記の例の中には、まだ奇跡の出会いは
なさそうです。笑
—————
考えを広げる:脱2択
—————
人は物事を単純化したいので、
なにかを2択で考えがちです。
ランチはラーメンにするか
牛丼にするか?
アイスコーヒーにするか
カフェラテにするか?
お風呂にするか
食事にするか?
(あれ…なんか食事系の話ばかり^^;)
ここで思考を広げるためには、
「A or B」ではなく「A and B」
を考えることです。
「ラーメンも牛丼も食べることが
できる方法はないだろうか?」
こういった発想から思考をスタートします。
参考までに、参考図書では
こんな事例が紹介されていました。
・夜勤明けのお父さんが家にいる日
・お母さんは買い物に行きたいけど、
幼い4人の子どもがいて、その日は悪天候
・子どもを連れて買い物に行くのも難しいが、
夜勤明けのお父さんは寝ている時間なので
子どもだけ置いていくことはできない
・すると、お父さんが「子どもの面倒は見るから
買い物に行ってきていいよ」とのこと
・その言葉に甘えて、お母さんは買い物へ
・家に帰ってくると、お父さんはリビングで
寝ていて、いつもは騒いでいる4人の子どもは
お父さんを囲んで、静かに絵を描いている
・実は、お父さんは子どもたちに「僕が寝ている
姿を一番よく絵に描けた子にチョコレートをあげる」
と言っていた
まさに、脱2択の賢い方法ですよね。
—————
考えを深める:ポジティブ価値化
—————
一見するとデメリットのものも
別の視点から見るとメリットに
見えるものがあります。
たとえば、
「仕事が遅い」という言葉は
ネガティブな印象を受けますが、
「仕事が丁寧」という言葉は
ポジティブな価値に見えます。
参考図書の事例ではこんな事例が
紹介されていました。
・アートディレクターの佐藤可士和氏は
キリンビールの発泡酒「極生」をヒット
させるための戦略を考えていた
・当時、発泡酒は当初ビールの一段下に
ある安いカテゴリーという位置づけを
されていた
・つまり、「ビールの廉価版」という
ネガティブなイメージがあった
・そこで、佐藤氏は発泡酒のポジティブな
立ち位置を築くことを最重要課題に設定した
・具体的には、
ビールの廉価版=カジュアルに楽しめる
現代的な飲み物
コクが足りない=ライトで爽やかな飲み口
といったポジティブな価値化をした
・「極生」はこの戦略によってヒット商品
として生まれ変わった
見かけ上の価値ではなく、
価値を多面的に突き詰めることで
考えを深めることができるという
ことですね。
ということで。
今回は、
「考えを広げて、深める」
という具体的な方法を
紹介しました。
もっと詳しく知りたい方は、
ブログ最下部に記載している
参考図書を読んでみてください。
最後に、冒頭の問題の答えです。
この答えは1つではありませんが、
最も簡単なのは、
「桐生になんの具材にしたかを聞く」
ということですね。笑
「考え方」がわかると、
こういった柔軟な発想もどんどん
出てくるようになるってことです。
桐生 将人
―参考図書:『パン屋ではおにぎりを売れ 想像以上の答えが見つかる思考法 地味だけど一生役立つ「考える技術」』著:柿内 尚文、出版:かんき出版 (2020/6/24)