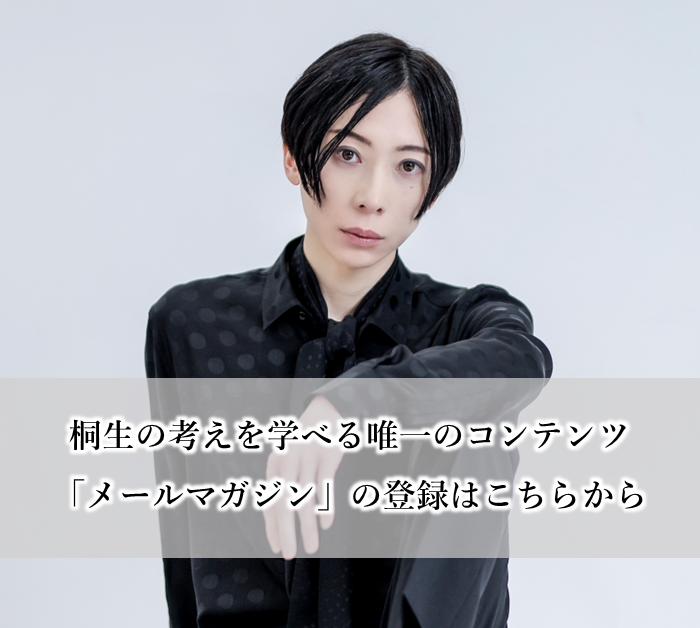※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
「ジョブ型雇用」って知っていますか?
最近よく耳にするようになりましたが、
海外では当たり前に導入されているもので、
要は「この仕事ができるから採用する」
みたいなイメージです。
ある意味では、外見、人柄、年齢、
勤続年数のような属人的な要素を
排除した公平感のある雇用形態だと
言えるかもしれません。
日本では、一般的に、
これとは逆のメンバーシップ型雇用
という方法が取られていて、
「まずは人を採用して、
その人に仕事を与えていく」
という方式が取られています。
簡単にまとめると、
・ジョブ型雇用とは、
まず必要な仕事を明確にしたうえで
その仕事ができる人を採用する
・メンバーシップ型雇用とは、
会社に合いそうな人を採用したうえで
その人に仕事を割り振る
ということになります。
このように比較してみると、
明らかに会社にとっては
ジョブ型雇用が合理的です。
逆に、雇用される側に立ってみても、
自分に合っていない仕事を
押し付けられることもありませんし、
スキルさえあれば、勤続年数や人柄
といった属人的な要素も排除できるので、
こちらも合理的だと言えます。
そんなわけでジョブ型雇用が進めば、
雇う側も雇われる側もハッピーな世界が
訪れそう!
と思っていたのですが、、、
実際の現場では、まったく
そんなことはないようです。
ジョブ型雇用が進んでいくと
どうなるか?
ジョブ型雇用はその仕事を
こなせる人物を採用します。
ですが、当然ながら、
その仕事をこなせる人は
自分1人ではありません。
そうなると、選ばれるためには
差別化できる何かが必要になります。
そもそも、ジョブ型雇用において、
その仕事をこなすスキルは持っているのは
当たり前ですから、差別化においては
それ以外の要素が求められます。
とはいえ、
まったくその仕事に関係ないスキルを
持っていても、その仕事に活かせない
ものなら価値にはなりません。
結果として、自分で差別化する
ことができなければ、
人柄や経験年数といった
わかりやすい要素や
本来業務以外も手伝ってくれる
ような使い勝手の良さ等で
判断されることが多くなって
いくことが予想されます。
なので、冒頭に書いたような
「スキルさえあれば公平に評価される」
「適正に合わないことはやらなくていい」
といったメリットはなくなっていく
わけです。
さらにいうと、
ジョブ型雇用には、
「その仕事がなくなればクビになる」
というデメリットがあります。
メンバーシップ型雇用の場合は、
人に仕事を割り振るので、
その仕事がなくなっても
会社が新たな仕事を用意します。
ですが、ジョブ型雇用の場合は、
仕事に人を割り振っているので、
その仕事がなくなれば、
その人も不要になるわけです。
このように考えると、
ジョブ型雇用が進んでいくと、
「今までの働き方のまま
クビにされやすくなった」
という残酷な社会へ突き進むだけ
と言えるかもしれません。
ですが、、、
こんなことは資格起業の世界だと
当たり前の話ですよね。
たとえば、社会保険労務士が
「会社と顧問契約をする」
というのは、
「人事労務の手続きや給与計算
といったジョブをこなす人として
会社に雇用される」
と言い換えることができます。
では、社会保険労務士の資格を取って、
人事労務の手続きや給与計算のスキルを
習得したら顧問契約をもらえるのかというと、、、
そんなことはないわけです。
社会保険労務士の資格を
持っている人は4万人以上いますし、
資格を持っていなくても
人事労務の手続きや給与計算の
仕事をこなせる人はもっと
たくさんいるでしょう。
その中で選ばれるためには
差別化が必要です。
資格を持っているとか
人事労務の業務ができるとか
そんなのはスタート地点で
しかありません。
当たり前の話だからです。
では、わかりやすい「経験年数」に
頼れるのかというと、、、
それも難しいですよね。
だからこそ、重要なのは、
1.士業としてのマインドを
しっかりと整えること
2.差別化の要素を繋ぎ合わせること
の2点です。
1.に関しては相手に専門知識が
なくてもわかりやすい要素なので、
避けては通れないものです。
簡単に言えば、クライアントに
「他ではないあなたに頼みたい」
と思ってもらえるように、
自分自身のマインドを整える
ということです。
『マインドが変わっても
結果は変わらないのでは?』
と思うかもしれませんが、
これがとんでもなく変わるのです。
桐生は、資格起業ラボで
“顧問契約をお願いされる
士業特有のマインド(=士業マインド)”
についてお伝えしています。
実は、資格起業ラボをスタートしたときに
最初に公開したのがこの「マインド」の
パートだったのですが、、、
営業法を何もお伝えしていない段階で、
これを学んだだけの参加者がどんどん
顧問契約を獲得できるようになって
しまったのです。
なぜ、そんなことが起きるか?
それは、
マインドが変わると
使う言葉が変わり、
行動が変わるからです。
独立開業している多くの
社会保険労務士や士業は、
一般的な「起業家マインド」を
持っているかもしれません。
ですが、そういった方々の中でも
「士業マインド」を体系的に理解して
いる方はほとんどいません。
そもそも、一般的な起業家と
顧問契約という長期型の契約を
お願いされる士業のマインドは
根本的に考え方が異なるのです。
よく桐生は、
「どんなノウハウを学んでも
顧問契約を依頼される士業に
なっていないと意味がない」
という話をします。
まず、顧問契約を依頼される
士業になるためにも、
ノウハウや経験以上に
「士業マインド」を理解することが
重要だということです。
では、2.についてですが、、、
っと、話が長くなりすぎたので、
次回にしようと思います。
ちなみに「士業マインド」に関しては、
資格起業ラボのメインコンテンツの
第8話で詳しく学べます。
興味がある方はチェックしてみて
ください!
↓資格起業ラボの詳細は今すぐこちらから↓
https://atelierkiryu.com/
桐生 将人
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
▼リニューアルして募集再開しました!▼
★資格起業ラボ★
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-