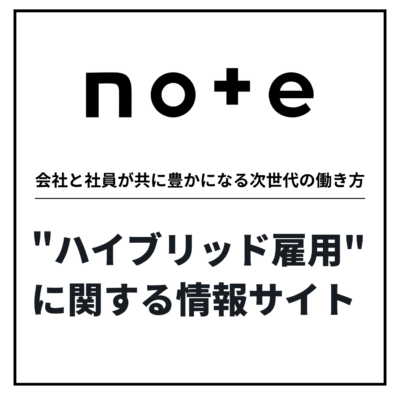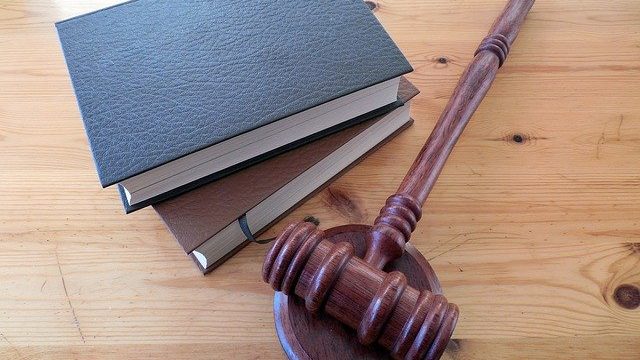※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
「社員が労基署に駆け込んでも
大丈夫なように顧問契約をしたい」
これは”社労士”という職業柄、
経営者の方からよくいただく
ご相談です。
確かに、法律の範囲内でルールを整備し、
トラブルを未然に防ぐのは重要なことです。
…ただし。
“労基署対策”だけに目を向けていると、
“いざ裁判になったときに会社が大損する”
なんてことになってしまうかもしれません。
一見すると、労務管理とは、
・まずは”労基署対策”をしっかりやって、
・そのうえで”裁判”まで発展した場合でも
戦えるようにしていく
というような”積み上げ”のように
感じるかもしれません。
もちろん、労務管理の中には
そういったものも多くあります。
ですが、「お金」にフォーカスを
あてると”そうではない”ことが
結構あるのです。
その代表的なものが「残業」です。
たとえば、管理職のスタッフが
毎月60時間の残業をしていたとします。
残業については労働基準法で、
・原則月45時間まで、
・特別な届出をしても45時間を
超えても良いのは年6回まで
となっています。
つまり、この状況だと法違反として
労基署調査で指摘を受けることに
なります。
とはいえ、人不足の会社であれば、
単純に「残業時間を減らしてくれ」
というだけでは無理があるかも
しれません。
では、残業時間を変えることなく
この問題を解決する方法があるのか
というと…
あります。
その1つが
「社員を管理監督者にする」
ということです。
その社員を管理監督者とすれば、
労働時間の規制を受けないことに
なるので、残業時間が月60時間だと
しても労基署から指摘を受けることは
なくなります。
労働時間の規制を受けなくなるので、
残業代を支払う必要もありません。
つまり、結果的に
「働き方を変えることなく
労基署対策を完了した」
と言えるのです。
『そんな裏ワザがあったのですね!
明日から全役職者を管理監督者にします!』
と、さすがにそこまで言う人はいないかも
しれませんが…^^;
ただ、あなたの会社の店長や所長といった
役職者だとしても、安易にこの方法を取る
のは非常に危険です。
というのも、裁判で争った場合、
管理監督者であることを否認される
可能性が非常に高いからです。
そもそも、管理監督者は
事前に行政に申請して認めてもらう
ようなものではありません。
そして、明確に
「この要件をクリアしたら
管理監督者として扱ってOK」
というものでもありません。
つまり、会社が
「この社員は管理監督者である」
と言ってしまえば、労基署対策は
完了するかもしれませんが、
もし、その後に社員から訴えれて
裁判に発展するようなことがあれば、
「実態として管理監督者と言えるのか」
が争われることになるわけです。
そして、もし、裁判で
管理監督者であることを否認されて
しまうと、会社は過去に遡って
未払の残業代を支払わなければ
ならなくなります。
しかも、これは
「滅多に起きないこと」
ではありません。
実際、判例などを見ていても、
管理監督者が認めらているケースは
かなり少ない印象で、
たとえ会社の役職者だったとしても、
実質役員レベルの権限や処遇がないと
認められないことが多いです。
しかも、それだけではありません。
実は、管理監督者にすることで、
裁判で負けたときのダメージが
増大するケースも多いです。
その理由は、
管理監督者を前提とすると、
・労働時間を管理しないので、
好き放題に残業ができてしまう
・残業代が発生しないという前提が
あるので「固定残業代」を設定しない
(むしろ、固定残業代を設定すると
管理監督者性を弱めることになる)
ということで、結果として、
残業時間が多くなり、
残業単価も高くなる傾向がある
からです。
逆に、もし、労基署対策として
安易に管理監督者にすることを
選んでいなければどうなっていたか?
まず、労働時間をおさえるために、
残業時間をしっかりと管理して、
生産性を高めることを考えます。
その結果、不要な残業時間を
抑えることができたかもしれません。
さらに、
「残業すれば残業代がもらえる」
というモチベーションを下げるために、
固定残業代を設定したかもしれません。
こういった王道の方法だと、
社員の働き方の意識を変える必要も
ある話なので、すぐに労基署対策が
できるわけではありません。
もしかしたら、なかなか改善が進まずに、
労基署から何度か指導を受けることになる
かもしれません。
ですが、そうだとしても、
裁判で争った場合はまったく
別の結果になります。
というのも、労働基準法に違反
しているからといって、いきなり
ものすごい罰金があるわけでは
ありません。
むしろ、お金の問題が起きるとすれば、
「残業に対してしっかりと
残業代が支払われているか」
というところになります。
そのように考えると、今回の場合、
管理監督者のパターンと同様に残業代を
支払っていなかったとしても、
・まず、残業時間をしっかりと
管理しているので、残業時間自体が
少なくなる可能性が高い
・固定残業代を払っている分は、
残業代を支払う必要はない
・固定残業代を設定している分、
残業単価が低くなる
ということで、
結果的に当初のパターンよりも
裁判での金銭的なリスクは遥かに
低く抑えられることになります。
ここからわかるのは、
「労基署の指摘をクリアすること
だけを考えて労務対策をすると、
裁判までいったときの金銭的な
リスクを逆に増やしてしまう
ことがある」
ということです。
だから、桐生は独立当初から一貫して、
「判例から逆算した労務対策」
というスタンスを取っているわけです。
そして、そういったスタンスの社労士が
いなかったからこそ、多くの方から
「他にはいない社労士」と言っていただけた
のかもしれません。
これからも桐生は、
「労務の分野で経営者のお金を守り、
そして、生み出す手法」
を突き詰めていきます。
あなたは労基署対策ばかり
考えていませんよね?
最終的なリスクは常に裁判である
ことを忘れずに!
桐生 将人