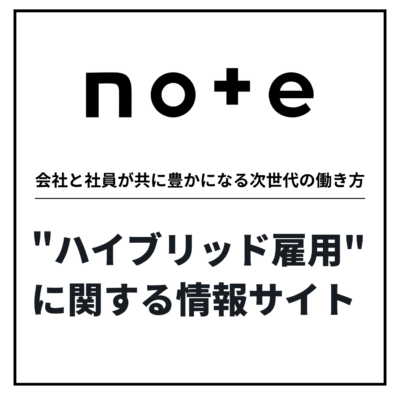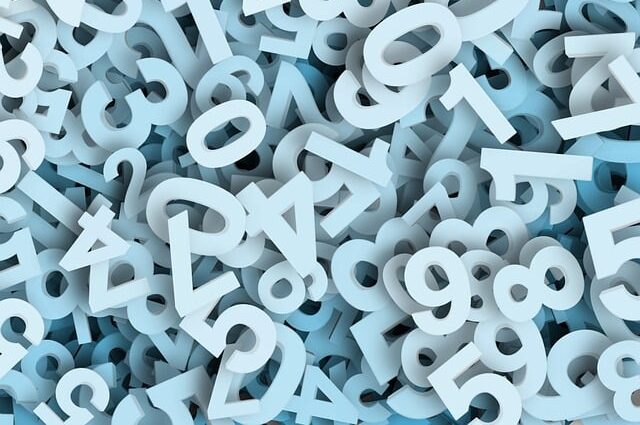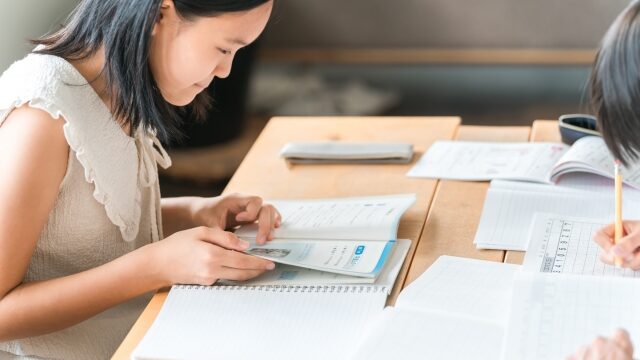※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
『え?桐生さん何言ってるの?
賞与も社会保険料はかかりますよ!』
そんな声が聞こえてきそうです。
ですが、賞与の社会保険料が
かからないことはあります。
たとえば、
・そもそも社会保険に加入して
いない社員
・産休や育休で社会保険料が
免除されている社員
等など…
これらの方は賞与をもらっても
社会保険料は1円もかかりません。
ですが、これらは特殊ケースと
言えるかもしれませんよね^^;
なので、今回はもう1つ。
ハイブリッド雇用によって
賞与をもらっても社会保険料が
かからなくする方法を考えて
みたいと思います。
先に言っておきますが、
今回はあくまでも理論上可能な
形を考える”思考実験”です。
ハイブリッド雇用は
“実態”がなにより重要です。
「安易に形だけを真似する」
といったことは絶対にしないで
くださいね。
————–
それでは、
思考実験のスタートです。
————–
まず、ハイブリッド雇用は、
フリーランス契約を中心として
社員としての雇用も継続します。
よって、今まで通り普通に
社員としての契約に対して
賞与を払えば社会保険料の
対象となってしまいます。
つまり、ポイントは、
「フリーランス契約に対して
賞与を払えるのか?」
ということになります。
実際、これはハイブリッド雇用の
導入を検討する経営者の方から
よくある質問の1つでもあります。
結論から申し上げると、
「フリーランス契約に対して
実質的に賞与を支払うことは可能」
だと言えます。
ただし、”実質的”と言ったように、
賞与の支払い方については見直す
必要があります。
そのうえで、まずは
「自社の賞与はどういう目的で
支払われているか」
を明確にすることが重要です。
一般的に、賞与が支払われる目的は
大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目は「年収を分割するため」、
2つ目は「成果報酬を支払うため」です。
この2つのそれぞれについて、
「どうやって賞与を実質的に支払うのか」
を見ていきましょう。
————–
「年収を分割するため」の賞与
————–
これは、たとえば、
「毎年夏と冬にそれぞれ1ヶ月分の
賞与を支払う」というように
“成果”というよりもむしろ、
年収を支払う”時期”を分けているに
過ぎない賞与のことです。
こういったケースであれば、
実際は給与的な側面が強いわけですから、
そもそも賞与にするのではなく、
フリーランス契約においては、
単純に12か月分割で支払うことを
検討すれば良いと言えます。
働く側も年収自体は変わりませんし、
賞与だった分が社会保険料の対象外に
なることを鑑みれば、会社・働く側の
どちらにとってもメリットがあります。
あるいは、他の方法として、
ハイブリッド雇用であれば
・フリーランス契約で12か月分の報酬
・社員の雇用契約で2か月分の給与
といった形も考えられるかもしれません。
というのも、ハイブリッド雇用は、
フリーランス契約が主軸となっているので、
日々の業務のほとんどはフリーランス契約で
成り立っているはずです。
なので、これまでの12か月分の給与を
フリーランス契約の報酬へと切り替えて、
残りの2か月分の賞与相当額は社員側の
給与として支払うという設計も考えられる
ということです。
————–
「成果報酬を支払うため」の賞与
————–
これは、完全に月給とは分離して
その社員があげた成果に応じて
支払っている賞与のことです。
成果報酬型の賞与に関しては、
ほぼ社員のときと同じように
支給することが可能です。
それどころか、その賞与は
「フリーランス契約に対して
支払う方が適している」
とすら言えるかもしれません。
というのも、
フリーランスとは本来、
「何時間働いたか」ではなく、
「どんな成果を納品したか」に対して
報酬を支払う仕組みだからです。
そう考えると、
「成果を出してくれたから、
利益の一部を分配する」
という意味での賞与であれば、
それをフリーランス契約に対して
支払ってもまったく違和感はない
と言えます。
ということで。
もし、あなたの会社が賞与制度を
導入しているのであれば、
社員の賞与の”手取り”を守るためにも
ぜひ一度「ハイブリッド雇用」の導入を
検討してみてください。
繰り返しになりますが、
今回の内容は理論上可能なことを
“思考実験”したに過ぎないものです。
安易に実態のない形だけの運用をすれば、
偽装請負による未払残業代の発生、
社会保険料の追徴、課税仕入れの否認等…
大きなリスクが生じます。
『社員のために次世代の働き方改革を
実現したい…』
『だけど、適正な運用できるか不安だ…』
そういう方こそ、ぜひ一度桐生に
ご相談ください。
桐生 将人