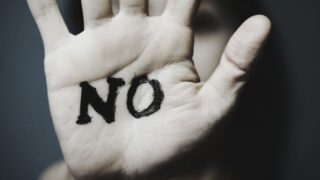※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した
内容を再編集して投稿しております。
こんにちは。
桐生です。
最近、経営者界隈でよく目にする
フレーズがあります。
それが
「給与を上げない賃上げ」
です。
要するに、
名目賃金(基本給や手当)は
据え置いたままで、
福利厚生の充実等で
“実質賃上げ”を実現しよう
という考え方です。
よくあるものとして
「食事代補助」
が挙げられます。
(社宅制度に関しては
桐生自身もよく使うもので、
それなりのメリットがある
ものだと思いますが、
企業にとってのリスクや
地域性の問題もありますので、
今回は触れません^^;)
具体的にどういう内容かというと…
・食事補助は「社員が1/2以上を負担し、
月額3,500円までの会社負担であれば、
非課税となる」
・つまり、会社が月3,500円昇給する
かわりに、食事代を月3,500円補助
してあげれば、給与をアップするより
税金が低くなる
といったものです。
最近では、この制度を使って
(結構大きい会社でも)
「節税になる!」
「社保がかからない!」
ということを堂々とメリットとして
打ち出している例も増えてきました。
ただ、、、
ここで思うことがあります。
『あれ…?なんか聞いたことがあるな』と。
そうです。
「ハイブリッド雇用」の根底にある考え方と
まったく同じなのです。
桐生がこの制度に込めている信念の一つに
「経営者に負担をかけずに、
社員の可処分所得を最大化する」
というものがあります。
まさに
「給与をあげない(=経営者の負担を増やさない)
賃上げ(=社員の可処分所得を増やす)」
と一緒だということです。
ぜひ、こういった流れがもっと大きくなって
いったらいいなぁと思ったのですが、、、
正直に言ってしまうと、
「福利厚生だけでは
インパクトが小さすぎる」
と考えています。
たとえば、先の事例の「食事補助」です。
3,500円分が非課税になったところで、
仮に税・社保の合計が30%だとすれば、
実質的な“節税額”は月1,050円。
しかも、食事の現物支給に該当するケースでは、
社会保険は対象外にならない可能性もあります。
つまり、手取りアップはほんのわずかだと
いうことです。
(会社にとってのメリットはもっと小さいです)
これが1000人、2000人規模の会社であれば
それなりのメリットがあるかもしれませんが、
多くの中小企業では、そのインパクトは
小さいと言わざるを得ません。
だからこそ、桐生は小さな会社ほど、
「もっとダイナミックに雇用制度をハックする」
必要があると考えています。
それができるのが「ハイブリッド雇用」です。
「ハイブリッド雇用」であれば、
月3,500円の非課税枠なんて小さな話ではなく、
事業としての業務委託部分で、通信費・交際費・
外注費などの経費計上が可能になります
(もちろん事業に必要な経費に限ります)。
また、社会保険料の負担についても、
契約内容によって実質的にコントロールが
可能になるといえます。
さらにいえば、
「ハイブリッド雇用」であれば、
今回の食事補助の福利厚生制度を社員の
身分の方に適用できる可能性もあります。
つまり、「ハイブリッド雇用」は
“給与を上げない賃上げ”のための
福利厚生制度の上位互換のようなもの
だということです。
こんなに小さな効果しかない制度が
ブームになっていることを見ていると、
「それだけ打ち手がないのだろうなぁ…」
と思わざるを得ません。
だからこそ、桐生は今本気で
「ハイブリッド雇用」の導入に
チャレンジしようと考えている
わけです。
これからも次世代の働き方
「ハイブリッド雇用」の開発者として、
積極的な情報発信を行っていきます。
楽しみにしていてくださいね^^
/////////////////
共創型顧問契約 個別相談
/////////////////
桐生が今本気で取り組んでいる
「日本の雇用制度をハックする」
というプロジェクトがあります。
これは、経営者と一緒になって
“次世代の雇用制度”を導入することで、
「会社の利益を生み出しながら、
社員の手取りも増やして、
社員が豊かになるための
投資資金も作り出す」
といった”働き方改革”を実現する
というものです。
そして、この実験的な制度の構築に一緒に
チャレンジしてくれる経営者の方に対して
「共創型顧問サービス」という特別な契約を
ご提案しています。
ご興味がある方には、導入可能性を判断する
ための個別相談を行っています。
個別相談を希望する場合は、
ぜひこちらのNoteからお申し込みください。
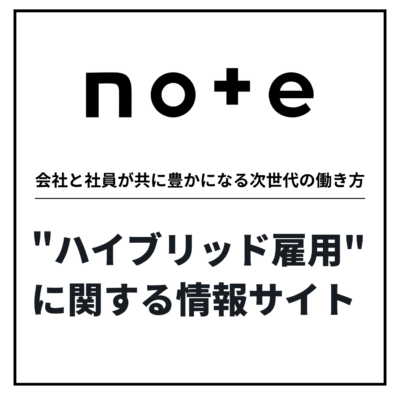
それでは、また!
桐生 将人